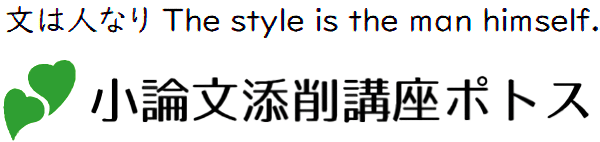接続詞 ゆえに、それゆえに、それゆえ
(定義)
推論(すいろん)の接続詞。
前に述べた事がらから、必然的に後の事がらが導かれることを表します。
漢字で書くと「故に」ですが、一般的に「ゆえに」「それゆえに」「それゆえ」は書くときはひらがなで書きます。
「それゆえに」の「それ」は前の事がらを指し、前の事がらが後の事がらの理由であることを強調した言い方になります。
「ゆえに」「それゆえに」は、数学、哲学、論文などで使われ、書き言葉的でかたい言い方です。
「それゆえ」は、「それゆえに」を略した少しくだけた言い方になります。
(例文)
【ゆえに】
・我思う。ゆえに我あり。
・3角形ABCは2つの辺が等しい。ゆえに二等辺三角形である。
・昔は下級武士の身分に生まれたがゆえに、能力があっても重要な職務につけなかった武士が多かった。
・彼は横綱であるゆえに負けることはゆるされない。
【それゆえに】
・日本は、島国である。それゆえに、大陸の文化の影響を受けつつも、日本独自の文化が大きく発展していった。
・「選挙」とは、私たちの生活や社会をよくしていく私たちの代表者を決めるものです。それゆえに、私たちは選挙に行く必要がある。
【それゆえ】
・日本人は選挙の意義について理解していない、もしくは、理解しようともしていない。それゆえ、日本は選挙に行かない人が多い。
・次の試合に負けたらJ2に降格してしまう。それゆえ、次の試合は絶対に勝たなければならない。
他の接続詞もこちらで解説しています。